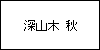TOP > ミステリの本棚(作家別Index) > 京極夏彦 > here
姑獲鳥の夏 (京極夏彦)
書籍情報
著者 : 京極夏彦
発行元 : 講談社
新書版発行 : 1994.9
文庫版発行 : 1998.9
単行本発行 : 2003.8
分冊文庫版発行 : 2005.4
京極先生のデビュー作。
「京極堂」こと中禅寺秋彦、探偵の榎木津礼二郎らがさまざまな妖怪にちなんだ事件を解決する「百鬼夜行シリーズ」の第一作。
講談社に持ち込まれたこの作品が、「メフィスト賞」創設のきっかけになったとも言われる。
こんな人にお薦め
- 妖怪、陰陽道などのキーワードに反応してしまうあなた
- 伝奇的作風がお好みなあなた
- この先に広がる超長編な世界に足を踏み入れたいあなた
あらすじ
以下、文庫版裏表紙より引用
-
この世には不思議なことなど何もないのだよ――古本屋にして陰陽師(おんみょうじ)が憑物を落とし事件を解きほぐす人気シリーズ第1弾。
東京・雑司ヶ谷(ぞうしがや)の医院に奇怪な噂が流れる。
娘は20箇月も身籠ったままで、その夫は密室から失踪したという。文士・関口や探偵・榎木津(えのきづ)らの推理を超え噂は意外な結末へ。
書評
無茶な展開をも納得させる圧倒的な世界観の構築
手を出すかどうか、しばらく迷っていた「京極堂」シリーズ。
迷っていた理由は言うまでもなく「分厚さ」!!
文庫版600ページ超のこの作品はもちろんですが、その本作品が薄く見えてしまう「百鬼夜行シリーズ」の面々。
ただ、世界最長の本格ミステリ「人狼城の恐怖」(二階堂黎人)を楽しく読破したわたしですから、それだけではありません。
というのも、このシリーズはなんだかニッポンの妖怪達が蠢く、推理小説というよりかは伝奇小説っぽい雰囲気。
いわゆる本格ミステリ好きのワタクシですので、手をこまねいていたのです。
が、解説などを読んでみると「探偵・榎木津」なる人物も登場するということで、おそらく本格ミステリの範疇に入るに違いないと判断し、読んでみることにいたしました。
結果。
わたしの選択は正しかった!!
確かに単純に本格ミステリとして見た場合、それほど大胆なトリックがあるわけでもなく、また、事前の予想通り幻想的な伝奇小説っぽい描写が多く、本格ミステリにリアリティを求める人にはきついかもしれません。
しかし、「この世には不思議なことなどなにもない」と言い切る京極堂の口を通じて語られる世界観、理論が、小説の中に現実世界とはまた違った一つの世界を見事に作り上げています。
この分厚い小説のかなりの部分が、民間伝承としての魑魅魍魎の意味や、人間の「意識」と「脳」の関連などを中心とした世界観の説明になっています。
そして、京極堂が語った世界観を読者の代わりに体験する役回りとして、記述者である関口が配置されています。
解説でも書かれていることですが、この関口の存在が、京極堂の理論を理論で終わらせずに、作品世界に結びつける役所として非常に重要だと思います。
現実的に考えて、そんなバカな、と思われても仕方がない京極堂の理論を、読者が客観的であると信じている記述者自身がことごとく体現してくれるものですから、読者の側にも京極堂の理論が、ただの理屈ではなく、実体を伴った世界観として迫ってくるのでしょう。
また、探偵・榎木津も、探偵というにはあまりにも特異ですねぇ。
なんせ「見えてしまう」のですから。
普通の本格ミステリでこれをやってしまうと、ネタバレ甚だしく、ミステリとして成立させるのは大変だと思うのです。
そして、この作品においても、確かにネタバレになってしまっている部分もあるようには思いますが、榎木津に見えるものが記述者・関口の認識とどうしようもないくらい一致しないので、それが新たな謎を引き起こすきっかけとなって、作品の重厚感が増していると思います。
物語としては、意外と単純な構造だったように感じます。
妖怪「姑獲鳥」という装飾がなければ、(怪奇色の強いミステリとしては)それほど意外な展開というわけでもなかったですし、上に書いたように榎木津の言動がある意味物語の中心的な謎を暗示してしまっていますので。
しかし、そんなことをものともしない、物語世界の雰囲気と、その世界に見事に溶け合った登場人物の描写に、どんどん引き込まれてしまいました。
妊娠20ヶ月を数え、動くこともできなくなった梗子の姿は明らかに怪異として描かれていますが、彼女を取り巻く姉・涼子、消えてしまった夫・牧朗、廃れてしまった産院を経営する両親、そして、むかし、彼女に牧郞の恋文を届けた記述者・関口――彼らはみんな普通に振る舞いながらも、どこか微妙な狂いを感じさせます。
そんな、狂ったままにかろうじてバランスを保っていた世界を、黒い装束に身を包んだ京極堂の憑き物落としが崩壊させるクライマックスは、陰惨で、怪奇的ながら、どこか美しく、絵巻物を見ているような気分で読み進めました。
その崩壊は、崩壊であると同時に精算であり、再生でした。
ある種悲惨な結末ではありながら、狂った世界が、あるべき姿へ戻ったというすがすがしさも感じさせます。
ミステリとして考えれば、論争が起こるのもやむを得ないトンデモ展開だったのですが、そんなことに囚われずに味わって欲しい、そんな、一つの世界の終焉でした。
それにしても、ある種堅苦しい理論、理屈が渦巻く文章にもかかわらず、ことのほか読みやすかったのには驚きました。
これなら、より分厚くなる自作以降も読んでみようという気になろうというものです……が、やはりあらためてちょっと覚悟を決めてから取りかかることになりそうです。
いわゆる京極理論の「記憶」「命」「意識」「脳」に関する部分は、どこかドグラ・マグラの「脳髄論」「胎児の夢」を彷彿とさせました。
ドグマグにおいても「脳髄はものを考えるところに非ず」と論じられていました。
これはそのまま、京極理論の「凡ての物質には〈物質的記憶〉がある」「脳は記憶の蔵ではなく、記憶の再生や編集を行うところだ」ということと通じるような気がします。
もちろん、京極理論はある意味ドグラ・マグラのそれよりも、かなり深化、分化しており、現実的な説得力を持ちます。
が、「人の意識」というものに深く切り込んだこの両作品が、似たようなアプローチをとっているところに、単なる虚構と割り切れない何かを感じてしまいます。
コメントをお願いします
ぜひ、この書評に対するあなたのコメントをお願いいたします!
こちらからどうぞ