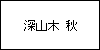TOP > ミステリの本棚(作家別Index) > 高里椎奈 > here
悪魔と詐欺師 薬屋探偵妖綺談 (高里椎奈)
書籍情報
著者 : 高里椎奈
発行元 : 講談社
単行本(ソフトカバー)発行 : 1999.12
文庫版発行 : 2006.6
落ち着いた好青年座木(くらき・通称 ザキ)、超美少年の深山木秋(ふかやまきあき・通称 秋)、赤毛で元気いっぱいな少年リベザルが営む「深山木薬店」を舞台にした「薬屋探偵妖綺談」シリーズの第3作。
こんな人にお薦め
- キャラ萌えな(特にリベザル好きな)あなた
- 読後に残った謎に悶々としたいあなた
- ファンタジー色の強い作品が好きなあなた
あらすじ
以下 文庫版裏表紙より引用
-
毒死した京都の外科医、轢死(れきし)した東京のプログラマー、失血死した鳥取の書店員…場所も日時も別々で互いに無関係な六人の死。自殺、事故死、殺人としてすべて解決したはずのこれらの事件の共通点とは何か?
薬屋探偵三人組の良心座木(くらき)が難攻不落の謎に挑む!個性派キャラが続々登場する好調シリーズ第3弾。
書評
読みやすさに甘えていると後悔します
読んでいる感覚は下手すればジュブナイル。
実際の年齢はともかく、悩める少年リベザルの葛藤と成長に焦点を当てた作品です。全体から受ける印象は、今までの2作に比べて対象年齢が低く感じました。少なくとも読んでいる間は……。
更に、元々読みやすい文章が更にこなれてきて、すいすい読めてしまうのでなおさらです。
……が!
甘かったです。
漫然と読み過ぎました。
ミステリとしての構成は、序盤からいろんな脈絡のなさそうな細かい事件が取り上げられ、それが最後につながってゆくというスタイルで、それ自体は特に目新しいものではなく、どうまとめていくのかな~といった気分で読み進めていました。そして、後半、一気に事件同士のつながりが明らかになってゆくのですが……ん?
で、結局犯人は?
謎の本当の核心部分が、シリーズの舞台設定を活かしたファンタジー色の強い表現で語られるため、はっきり言って、わかりません。
ファンタジーなトリックというわけでなく、「人間の事件」の描写をファンタジーというベールで覆ってしまったような感じといえばよいのでしょうか。
なんだかわかりそうでわからない。ミステリ愛好家としては最もつらい展開であります。
そのあたりが、この作品に関して「これはミステリではなくファンタジーだ」と評される方が多い一因でしょうか?(少なくとも私はそういう評価を良く目にしました)
最後の最後で欲求不満の杯を突きつけられながら。
「秋! 頼むからもう少しヒトに優しい名探偵になってくれ!」
そう叫びかけながら。
そして、そのラストの意味を考えながら。
でも、それと同時に思い起こしていました。
「そういやなんだか伏線くさいシーンいっぱいあったよな~」
そうなのです。
ラストにつながるあからさまなシーンが多数あったにも関わらず、私は文章の読みやすさにかまけて「謎は作者が教えてくれるさ♪」とばかりに、軽く読み飛ばしてきたのでした。
おそらくこの事件の本当の経緯は、本格ミステリになれている方にとっては、おそらくそれほど複雑なものでなく、むしろ、安直に感じてしまうものであるような気がします。
実際、複数の事件をつなぐ糸の解明においては、そんな単純な考察でいいの?と感じてしまいました。だから意地悪な言い方をすれば、単純に人間の視点で真相が語られたときには、ミステリとしての水準はそれほど高くないのかもしれません。
が、それは逆に言えば、読み手が注意深く考察しながら読んでいれば、ラストのぼかした表現にも関わらず、自分なりの真相に到達できるレベルだったのかもしれないのです。
なんだか届きそうで届かない。
もう一度きちんと読まないとガマンなりません!
なんだか「してやられた」といった気分ですので。
それにしてもキャラクターの個性はますます際だってきました。
特にリベザルの無垢っぷりや、ザギの色男っぷりなどはちょっと大げさになってきたようにすら感じます。
脇役の高遠や葉山両刑事も前作「黄色い目をした猫の幸せ」で得た存在感に磨きをかけ、欠かすことのできない「探偵の協力者」としての地位を確立したように思います。
そんな中、秋は意外と地味な変化です。
でも、すべての言動からは、その奥に潜む思慮が滲み出ます。はじめは単なる暴君(!?)だったと思うのですが、どんどん優しくなっています。悩めるリベザルの歩む道を整えながらも、自分自身でその道を見つけるように導くその振る舞いに、大きな魅力を感じます。
総評。
自分自身の読み込みの甘さを棚に上げてしまいますが、純粋にミステリとして考えると、やはり掘り下げ方は浅いように感じます。複数の事件が一つに収束してゆく過程の描き方が乱暴で、唐突な感じだったので、カタルシスを感じることはありませんでした。
でも、小説は別に純粋なミステリである必要性が、そもそもありません。
あたりまえですが。
賛否両論あるところだと思いますが、あの結末の描き方は、まったくわけがわからないわけでもなく、単純に真相を述べているものでもなく、最後の最後で安心しかけている読者を、もう一段階作品側に引き寄せる、絶妙のバランスであったように思います。
しかもそのファンタジー的表現は唐突なものではなく、独特の作品世界をうまく利用したものであり、活き活きとした登場人物達とあいまって、キラリと光るひとつの物語として読者の前にその姿を見せてくれています。
良い「物語」でした。
コメントをお願いします
ぜひ、この書評に対するあなたのコメントをお願いいたします!
こちらからどうぞ