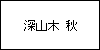TOP > ミステリの本棚(作家別Index) > 西尾維新 > here
クビシメロマンチスト 人間失格・零崎人識 (西尾維新)
書籍情報
著者 : 西尾維新
発行元 : 講談社
新書版発行 : 2002.5 講談社ノベルス
文庫版発行 : 2008.6 講談社文庫
戯言使いの「ぼく」を語り部とする「戯言シリーズ」第二弾。
今回は「ぼく」と殺人鬼・零崎人識の出会いと、その周辺で起きた「ぼく」のクラスメート達の殺人劇。
こんな人にお薦め
- ひと味違う。それでもあくまでも本格ミステリな本をお望みのあなた
- 本屋さんであの派手な表紙がこっぱずかしくて迷ってしまっているあなた
- 萌えキャラがヒドイ目にあってもミステリだから仕方ないと言えるあなた
あらすじ
文庫版カバーそでより引用
-
人を愛することは容易いが、人を愛し続けることは難しい。
人を殺すことは容易くとも、人を殺し続けることが難しいように。
生来の性質としか言えないだろう、どのような状況であれ真実から目を逸らすことができず、ついに欺瞞なる概念を知ることなくこの歳まで生きてきてしまった誠実な正直者、つまりこのぼくは、五月、零崎人識という名前の殺人鬼と遭遇することになった。
それは唐突な出会いであり、また必然的な出会いでもあった。
そいつは刃物のような意志であり、刃物のような力学であり、そして刃物のような戯言だった。その一方で、ぼくは大学のクラスメイトとちょっとした交流をすることになるのだが、まあそれについてはなんというのだろう、どこから話していいものかわからない。
ほら、やっぱり、人として嘘をつくわけにはいかないし――
戯言シリーズ第二弾。
書評
ようやく真価を見せはじめる「ぼく」
さて、戯言シリーズ第二作の本作。
「ぼく」と玖渚友(くなぎさ とも)を中心にした前作とは打って変わって、この作品は「ぼく」と殺人鬼・零崎人識(ぜろざき ひとしき)を中心に据えた物語となっております。
とは言っても、華麗にナイフを操る零崎人識は、物語開始時点で六人もの人間を殺戮している京都連続殺人の張本人であるにもかかわらず、何の暗さもなく、ただ、殺人者としての人生のレールの上を飄々と走り続ける存在。
そんな零崎に「そっくりさん」と呼ばれた「ぼく」は、今回は学生らしく、大学のクラスメイトの四人組――巫女子ちゃん、むいみちゃん、秋春君、智恵ちゃん――と関わり、智恵ちゃんの誕生パーティに参加することに。
……と言っても「ぼく」は巫女子ちゃんから話しかけられるまで、彼らのことを全く覚えて……認識して? いなかったわけですが。
なんか記憶力がないのが極端になってきました。
それにしても、なんだか学園系のゲームのヒロインみたいに萌え萌えで主人公に思いを寄せる巫女子ちゃん。
鈍感でそれに気付かない「ぼく」
ぶっきらぼう(乱暴とも言う)なのに巫女子ちゃんのことを影ながら大切に思う親友のむいみちゃん。
ちょっと軽いけど憎めないよき友人タイプの秋春君。
そして、どこか人から孤立したような、諦観にも似た雰囲気を持つ、ミステリアス系担当の知恵ちゃん。
なんて楽しそうなベタベタなシチュエーション……だったんですけどねぇ。
パーティ会場である知恵ちゃんのマンションで起こる殺人。
みんなが帰ったあとの殺人は、行きずりの犯行とは思えないものの、「ぼく」たちのアリバイは万全です。
あまりミステリとしての細かいディテールにこだわってはいないような感じですが、骨格はなかなかどうしてしっかりしております。
あるいはトリックとしてはそれほど難易度は高くないのかも知れませんが、語り部の「ぼく」の戯言に、結果的に翻弄される方が多いのではないでしょうか?
興味はないのに放置するわけでもなく、むしろ積極的に関わりながら、傍観者のようでいて、その言葉が人を刺す。
殺人者に関心もない顔をしながら、いや、無関心だからこそ誰よりも厳しい糾弾を与える。
こんな訳のわからない「ぼく」の視点だからこそ、本来ミステリとしてそれほど入り組んでいるわけでもないこの事件に、読者は惑わされるのでしょう。
あえて言ってしまえば、地の文でも嘘をつきまくりな「ぼく」なのですが、それが全く不自然ではない造形になっており、それがわかったあとにも、アンフェアだとは思わせない絶妙の記述になっています。
前作では、まだただの冷めた目を持つ傍観者的な探偵役――探偵役が、望まざる事件に嫌々巻き込まれていくというよくあるパターン――なのかな、とも受け取れるくらいの印象を「ぼく」に持っていたのですが、だんだん本性が見えてきました。
その性格を言葉でうまく説明できないのがもどかしいのですが、そんな壊れた「ぼく」がすんなり溶け込めるセカイ。
そう。
やっぱりそのセカイが魅力的。
前作のレビューでも書きましたが、竹先生の極彩色なイラストがどんぴしゃに似合ってしまうセカイなのです。
しかも、その極彩色は、混ぜても混ざらない。
魅力的だけれども……そのセカイでは定石なら守られるはずのものが、あまりに無造作に壊されてゆきます。
でも、元々壊れたセカイは、壊れたものをこそ違和感なく取り込む懐を持っています。
それが救いだと。
そう思いましょう。
まともに見れば、面白いけど後味はよくないはずの結末なのですが、そんな結末をも自然の流れかのように読者に感じさせてくれるのはさすがです。
すみません。
なんだかこの作品は、感想を書いていると、締まりなく移ろう書評になってしまいます。
ので、最後にまとめを。
とにかく、シリーズとして評判を見るに、この先ますますミステリ色は薄くなっていきそうですが、この作品はある意味賞レース向きな典型的ミステリの前作よりも、内面的な意味では、より戯言シリーズらしい世界観が前面に出ており、なおかつミステリとしても、意外と正当派で、ワタシとしてはとても好きな作品です。
普通にミステリファンの方にオススメできる作品でした。
それにしても、赤い人イイですねw
コメントをお願いします
ぜひ、この書評に対するあなたのコメントをお願いいたします!
こちらからどうぞ