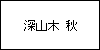TOP > ミステリの本棚(作家別Index) > 夢野久作 > here
ドグラ・マグラ (夢野久作)
書籍情報
著者 : 夢野久作
発行元 : 角川書店
文庫版発行(上下巻) : 1976.10
* 初版刊行は1935年1月、松柏館書店より書き下ろし作品として。
小栗虫太郎「黒死館殺人事件」、中井英夫「虚無への供物」と並んで「日本探偵小説三大奇書」と称される作品。構想、執筆には実に10年以上の歳月がかけられており、夢野久作はこの作品を発表した翌年、1936年3月11日、脳溢血により急死している。
こんな人にお薦め
- 狂人の素質があるあなた
- 「奇書」という響きにロマンを感じるあなた
- ありきたりのミステリでは物足りないあなた
あらすじ
以下、文庫版裏表紙より引用
-
「ドグラ・マグラ」は、昭和10年1500枚の書き下ろし作品として出版され、読書界の大きな話題を呼んだが、常人の頭では考えられぬ、あまりに奇抜な内容のため、毀誉褒貶(きよほうへん)が相半ばし、今日に至るも変わらない。
〈これを書くために生きてきた〉と著者自ら語り、10余年の歳月をかけた推敲によって完成された内容は、著者の思想、知識を集大成する。これを読むものは一度は精神に異常をきたすと伝えられる、一大奇書。
精神病院の一室で目覚めた「私」には記憶がない。
その部屋を囲むコンクリート壁の向こうからは若い女の叫びが「私」に呼びかける。
「……お兄さま。お兄さま。お兄さま、お兄さま、お兄さま、お兄さま、お兄さま。……モウ一度……今のお声を……聞かしてエーッ……」
愕然とする「私」に更に語りかけるその声。
「……あたしはお兄様とご一緒になる前の晩に……結婚式を挙げる前の晩の真夜中に、お兄様のお手にかかって死んでしまったのです。……それがチャント生き返って……お墓の中から生き返ってここにいるのですよ」
その後病室に現れた、大学の医学部長、若林に導かれ、何が正常で何が狂っているのかわからないまま、自分の正体を追いかけ始める「私」
その「私」の前に、若い精神病患者である大学生が一気に書き上げたものだという「ドグラ・マグラ」なる大部の原稿が現れ、現在、そして過去の事件があらわになるにつれ、現在の事件の犯人「呉一郎」こそが「私」の正体であるような……そうでないような……。
進めば進むほど迷宮の深部にはまり込むような錯覚。
なにが現実なのか、すべてが夢なのか、時の流れとは何なのか、「私」は誰なのか。
……「私」など存在しているのだろうか?
すべては「胎児の夢」……?
現実と夢
現実と虚構
現在と過去
すべてが渾然と語られる、奇書の名にふさわしい物語。
書評
胎児の夢
胎児よ
胎児よ
何故躍る
母親の心がわかって
おそろしいのか
この冒頭歌から始まるこの作品。
私にとって、小栗虫太郎先生の「黒死館殺人事件」に続く三大奇書への挑戦です。
お断りしておきますが、今回は書評の体裁にならないかもしれません。
なぜなら、とても初読でわかったようなことは書く気にならないからです。
と、こう書くと黒死館殺人事件を読んだ人、もしくはこのサイトの黒死館殺人事件の書評を読んでくださった方なら「これもまた、まったく訳のワカラン本なのか!?」と思われるかもしれませんが、それは間違いです。
「黒死館」は全編にわたるペダントリーによって、真剣に読んでもそもそも言葉の意味がわからないことだらけで、どうにも太刀打ちできない、といった意味のわからなさだったのですが、意外にもドグラ・マグラは一部を除いてそれほど難しい文言や文章ではありません。
一部研究論文めいた部分がありますので、そのあたり最近の軽い文体の物語しか読まない人にとっては多少しんどいかもしれませんが、それでも少々読みにくいというレベルですので、くれぐれも「難しそうだからパス」という結論は出さないでいただきたいです。
一読者の私がそれほど押しつけがましい言い方をするほどに、この本には一読の価値があります。
ただし、なんと言っても「三大奇書」です。
普通の本格ミステリを読むつもりで読み進めてしまうと、あまりの怪奇的な展開にかえって「これはルール違反だ!」なんていって放り出してしまうような気もいたしますので、あくまでも「奇書」を読み解くのだ、という感じで読んでいただければよいのではないでしょうか?
では、どの辺が奇書なのでしょうか?
ストーリー?いえいえ、この物語の物語的な大枠は、記憶喪失の「私」が誰なのか、「私」は殺人犯だったのか、同じ精神病院に入れられている美しい女性は、本当に「私」の許嫁で……そして、「私」は彼女を「殺した」のか?といった感じで、ちょっとサイコホラー的な香りはするけれど、充分推理小説だと言える枠組みなのです。
じゃあ、オカルト的なの?
いやぁ、これも私は違うと思います。決して、オカルトでもホラーでもありません。この大部の作品のかなりの部分を占めているのは「科学」なのです。それも昭和初期の一作家が書いたとは信じられないほどの克明さと、高い見識に依った精神医学、遺伝と進化、「夢」の構造、脳髄論なのです。〈現代科学に照らして「正確」という意味ではありませんが〉
結局、この本の「奇書」たるゆえんは、上のあらすじの最後に書いたことに重なると私は思います。
現実と夢、現実と虚構、現在と過去、そのすべてがいろんな色の絵の具を軽く混ぜた状態のように、不調和なまだらを描きながらも、その全体が明らかにひとつの模様として読者の観念を塗りつぶしてしまうのです。
この物語の前半には「ドグラ・マグラ」なる精神病患者の青年が書いた原稿が登場します。
そして、その作中作の「ドグラ・マグラ」の記述なのか、作中の現実として書かれているのか必ずしも判別できない状態で、大学の精神病科主任教授の正木先生の行動記録や論文、取材記事らしき文章が登場します。
「キチガイ地獄外道祭文」
「地球表面は狂人の一大解放治療場」
「絶対探偵小説 脳髄はものを考えるところに非ず」
「胎児の夢」
「空前絶後の遺言書」
これらのタイトルをみただけでも頭がクラクラしそうですが、問題は書かれていることが、非現実的なのに「とても科学的説得力がある」ことなのです。私の場合、途中で推理小説を読んでいるという感覚すら忘れて、その論文に読みふけっていました。
そして、その世界に深く足を踏み入れた結果、物語の一見支離滅裂な構成も、時間の観念を無視したような場面転換も自然な流れとして吸収され、そして後半で語られる楊貴妃の時代の殺人者「呉青秀」の事件と「腐敗美人図」と現在の殺人者「呉一郎」とその奇妙な犯行の心理遺伝的つながりなどという、一歩間違えれば荒唐無稽以外の何者でもないような展開さえ自然に受け入れてしまっていたのです。
さらに二転三転する物語を整理すればしようとするほど、自分がまさしく「胎児の夢」を見せられているような錯覚にさえ捕らわれます。
まるで、夢と現実を区別すること、現実と虚構を見分けること、時間の観念……そういったものすべてが無意味であると刷り込みをされているような感覚です。
ああ……。
書いていてわけがわからなくなってきました。
あらかじめ書評の体裁をなさないと断っておきましたので、この辺でご勘弁ください。
またいずれ再読します。
その時にはもっと書評らしく書けるかも。
……といいつつ、もっと深い迷宮に捕らわれそうな予感も……。
奇書ですよ?
コメントをお願いします
ぜひ、この書評に対するあなたのコメントをお願いいたします!
こちらからどうぞ